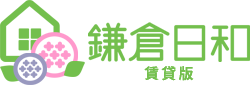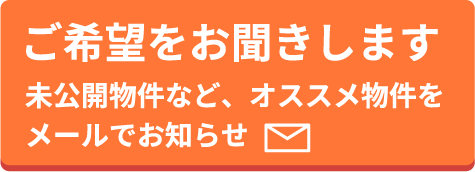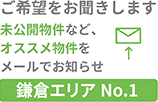鎌倉日和のお散歩ブログ
鎌倉日和【おぢいさんのランプとウォール街】

ウォール街のトレーダーやファンドマネージャーにリストラの嵐が吹き荒れているという話を聞きました。
少し前までは、桁違いの報酬を得て、飛ぶ鳥を落とす勢いだった人たちが今やその職場から姿を消している・・・
AIなどのテクノロジーの発達でこれまで知的労働と言われた分野の仕事が次々とコンピュータに取って代わられていて、あるアメリカの金融機関では600人いたトレーダーたちが、今や3人になったという話もあるそうです。
そういう話を聞くと、昔読んだ『おぢいさんのランプ』(新見南吉)を思い出します。
おぢいさんのランプ
かくれんぼで、倉の
出て来た。
それは珍らしい形のランプであった。八十
台になっていて、その上にちょっぴり火のともる部分がくっついている、
そしてほやは、細いガラスの筒であった。はじめて見るものにはランプ
とは思えないほどだった。
そこでみんなは、昔の鉄砲とまちがえてしまった。
「何だア、鉄砲かア」と鬼の
東一君のおじいさんも、しばらくそれが何だかわからなかった。
ランプであることがわかると、東一君のおじいさんはこういって
子供たちを
「こらこら、お前たちは何を持出すか。まことに子供というものは、
黙って遊ばせておけば何を持出すやらわけのわからん、油断もすきもない、ぬすっと
たちは外へ行って遊んで来い。外に行けば、
こうして叱られると子供ははじめて、自分がよくない行いをしたことが
わかるのである。そこで、ランプを持出した東一君はもちろんのこと、
何も持出さなかった近所の子供たちも、自分たちみんなで悪いことをしたような顔をして、すごすごと外の道へ出ていった。
外には、春の昼の風が、ときおり道のほこりを吹立ててすぎ、のろのろ
と牛車が通ったあとを、白い
あった。なるほど電信柱があっちこっちに立っている。しかし子供たち
は電信柱なんかで遊びはしなかった。
ことを、いわれたままに遊ぶというのは何となくばかげているように
子供には思えるのである。
そこで子供たちは、ポケットの中のラムネ玉をカチカチいわせなが
ら、広場の方へとんでいった。そしてまもなく自分たちの遊びで、
さっきのランプのことは忘れてしまった。
日ぐれに東一君は家へ帰って来た。奥の
がおいてあった。しかし、ランプのことを何かいうと、またおじいさん
にがみがみいわれるかも知れないので、黙っていた。
夕御飯のあとの退屈な時間が来た。東一君はたんすにもたれて、
ひき出しのかんをカタンカタンといわせていたり、店に出てひげを
むつかしい名前の本を番頭に注文するところを、じっと見ていたりした。
そういうことにも飽くと、また奥の居間にもどって来て、おじいさん
がいないのを見すまして、ランプのそばへにじりより、そのほやを
はずしてみたり、五銭
出したりひっこめたりしていた。
すこしいっしょうけんめいになっていじくっていると、またおじいさん
にみつかってしまった。けれどこんどはおじいさんは叱らなかった。
ねえやにお茶をいいつけておいて、すっぽんと
こういった。
「東坊、このランプはな、おじいさんにはとてもなつかしいものだ。
長いあいだ忘れておったが、きょう東坊が倉の隅から持出して来たので、
また昔のことを思い出したよ。こうおじいさんみたいに年をとると、
ランプでも何でも昔のものに出合うのがとても
東一君はぽかんとしておじいさんの顔を見ていた。おじいさんは
がみがみと叱りつけたから、
に
「ひとつ昔の話をしてやるから、ここへ来て
とおじいさんがいった。
東一君は話が好きだから、いわれるままにおじいさんの前へいって
坐ったが、何だかお説教をされるときのようで、いごこちがよくない
ので、いつもうちで話をきくときにとる姿勢をとって聞くことにした。
つまり、寝そべって両足をうしろへ立てて、ときどき足の裏を
うちあわせる
おじいさんの話というのは次のようであった。
今から五十年ぐらいまえ、ちょうど日露戦争のじぶんのことである。
巳之助は、父母も兄弟もなく、
まったくのみなしごであった。そこで巳之助は、よその家の走り使い
をしたり、女の子のように
そのほか、巳之助のような少年にできることなら何でもして、
村に置いてもらっていた。
けれども巳之助は、こうして村の人々の御世話で生きてゆくことは、
ほんとうをいえばいやであった。子守をしたり、米を搗いたりして一
生を送るとするなら、男とうまれた
男子は身を立てねばならない。しかしどうして身を立てるか。巳之助
は毎日、ご飯を
お金もなかったし、またたといお金があって本を買ったとしても、
読むひまがなかった。
身を立てるのによいきっかけがないものかと、巳之助はこころ
ひそかに待っていた。
すると
頼まれた。
その
でゆられていったもので、岩滑新田はちょうどその道すじにあたって
いたからである。
人力車は人が曳くのだからあまり速くは走らない。それに、
岩滑新田と大野の間には
おまけにその頃の人力車の輪は、ガラガラと鳴る重い
のである。そこで、急ぎの客は、賃銀を
にひいてもらうのであった。巳之助に先綱曳を頼んだのも、急ぎの
避暑客であった。
巳之助は人力車のながえにつながれた綱を肩にかついで、夏の
気にしなかった。好奇心でいっぱいだった。なぜなら巳之助は、
物ごころがついてから、村を一歩も出たことがなく、峠の向こうに
どんな町があり、どんな人々が住んでいるか知らなかったからである。
日が暮れて青い
人力車は大野の町にはいった。
巳之助はその町でいろいろな物をはじめて見た。
続いている大きい商店が、第一、巳之助には珍らしかった。巳之助の
村にはあきないやとては一軒しかなかった。
たいていの物を売っている小さな店が一軒きりしかなかったのである。
しかし巳之助をいちばんおどろかしたのは、その大きな商店が、
一つ一つともしている、花のように明かるいガラスのランプであった。
巳之助の村では夜はあかりなしの家が多かった。まっくらな家の中を、
人々は盲のように手でさぐりながら、
さぐりあてるのであった。すこしぜいたくな家では、おかみさんが
張りめぐらした中に、油のはいった
のぞいている
まわりの紙にみかん色のあたたかな光がさし、附近は少し明かるく
なったのである。しかしどんな行燈にしろ、巳之助が大野の町で
見たランプの明かるさにはとても及ばなかった。
それにランプは、その頃としてはまだ珍らしいガラスでできていた。
巳之助にはいいもののように思われた。
このランプのために、大野の町ぜんたいが竜宮城かなにかのように
明かるく感じられた。もう巳之助は自分の村へ帰りたくないと
さえ思った。人間は誰でも明かるいところから暗いところに帰る
のを好まないのである。
巳之助は
お酒にでも酔ったように、波の音のたえまないこの海辺の町を、
珍らしい商店をのぞき、美しく明かるいランプに見とれて、
さまよっていた。
呉服屋では、番頭さんが、
ランプの光の下にひろげて客に見せていた。
ランプの下で
は女の子が、ランプの光の下に白くひかる貝殻を散らしておはじきを
していた。また或る店ではこまかい
ランプの青やかな光のもとでは、人々のこうした生活も、物語か
世界でのように美しくなつかしく見えた。
巳之助は今までなんども、「文明開化で世の中がひらけた」という
ことをきいていたが、今はじめて文明開化ということがわかった
ような気がした。
歩いているうちに、巳之助は、様々なランプをたくさん
ある店のまえに来た。これはランプを売っている店にちがいない。
巳之助はしばらくその店のまえで十五銭を握りしめながらためらって
いたが、やがて決心してつかつかとはいっていった。
「ああいうものを売っとくれや」
と巳之助はランプをゆびさしていった。まだランプという言葉を
知らなかったのである。
店の人は、巳之助がゆびさした大きい
、それは十五銭では買えなかった。
「負けとくれや」
と巳之助はいった。
「そうは負からん」
と店の人は答えた。
「
巳之助は村の雑貨屋へ、作った
ので、物には卸値と
知っていた。たとえば、村の雑貨屋は、巳之助の作った
草鞋を卸値の一銭五
で売っていたのである。
ランプ屋の主人は、見も知らぬどこかの小僧がそんなことをいった
ので、びっくりしてまじまじと巳之助の顔を見た。そしていった。
「卸値で売れって、そりゃ相手がランプを売る家なら卸値で売って
あげてもいいが、一人一人のお客に卸値で売るわけにはいかんな」
「ランプ屋なら卸値で売ってくれるだのイ?」
「ああ」
「そんなら、おれ、ランプ屋だ。卸値で売ってくれ」
店の人はランプを持ったまま笑い出した。
「おめえがランプ屋? はッはッはッはッ」
「ほんとうだよ、おッつあん。おれ、ほんとうにこれからランプ屋
になるんだ。な、だから頼むに、
売ってくれや。こんど来るときゃ、たくさん、いっぺんに買うで」
店の人ははじめ笑っていたが、巳之助の真剣なようすに動かされて
、いろいろ巳之助の身の上をきいたうえ、
「よし、そんなら卸値でこいつを売ってやろう。ほんとは卸値でも
このランプは十五銭じゃ売れないけど、おめえの熱心なのに感心した。
負けてやろう。そのかわりしっかりしょうばいをやれよ。
うちのランプをどんどん持ってって売ってくれ」
といって、ランプを巳之助に渡した。
巳之助はランプのあつかい方を一通り教えてもらい、
ついでに
花のように明かるいランプをさげていたからである。
巳之助の胸の中にも、もう一つのランプがともっていた。
文明開化に遅れた自分の暗い村に、このすばらしい文明の利器を
売りこんで、村人たちの生活を明かるくしてやろうという希望の
ランプが――
巳之助の新しいしょうばいは、はじめのうちまるではやらなかった。
百姓たちは何でも新しいものを信用しないからである。
そこで巳之助はいろいろ考えたあげく、村で一軒きりのあきないや
へそのランプを持っていって、ただで貸してあげるからしばらく
これを使って下さいと頼んだ。
雑貨屋の
ランプを吊し、その晩からともした。
五日ほどたって、巳之助が草鞋を買ってもらいに行くと、
雑貨屋の婆さんはにこにこしながら、こりゃたいへん便利で明かるうて
、夜でもお客がよう来てくれるし、
、気に入ったから買いましょう、といった。その上、ランプのよいこと
がはじめてわかった村人から、もう三つも注文のあったことを
巳之助にきかしてくれた。巳之助はとびたつように喜んだ。
そこで雑貨屋の婆さんからランプの代と草鞋の代を受けとると
、すぐその足で、走るようにして大野へいった。そしてランプ屋の
主人にわけを話して、足りないところは貸してもらい、
三つのランプを買って来て、注文した人に売った。
これから巳之助のしょうばいははやって来た。
はじめは注文をうけただけ大野へ買いにいっていたが、少し金が
たまると、注文はなくてもたくさん買いこんで来た。
そして今はもう、よその家の走り使いや子守をすることはやめて
、ただランプを売るしょうばいだけにうちこんだ。
わくのついた車をしたてて、それにランプやほやなどをいっぱい吊し
、ガラスの触れあう涼しい音をさせながら、巳之助は自分の村や附近の
村々へ売りにいった。
巳之助はお金も
たのしかった。今まで暗かった家に、だんだん巳之助の売ったランプ
がともってゆくのである。暗い家に、巳之助は文明開化の明かるい火
を一つ一つともしてゆくような気がした。
巳之助はもう青年になっていた。それまでは自分の家とてはなく、
区長さんのところの軒のかたむいた
小金がたまったので、自分の家もつくった。すると世話してくれる人が
あったのでお
きいていたことをいうと、お客さんの一人が「ほんとかン?」と
ききかえしたので、
なり、区長さんのところから古新聞をもらって来て、ランプの下にひろげた。
やはり区長さんのいわれたことはほんとうであった。
新聞のこまかい字がランプの光で一つ一つはっきり見えた。
「わしは嘘をいってしょうばいをしたことにはならない」と巳之助は
ひとりごとをいった。しかし巳之助は、字がランプの光ではっきり
見えても何にもならなかった。字を読むことができなかったからである。
「ランプで物はよく見えるようになったが、字が読めないじゃ、まだ
ほんとうの文明開化じゃねえ」
そういって巳之助は、それから毎晩区長さんのところへ字を教えて
もらいにいった。
熱心だったので一年もすると、巳之助は
誰にも負けないくらい読めるようになった。
そして巳之助は
巳之助はもう、男ざかりの
「自分もこれでどうやらひとり立ちができたわけだ。まだ身を立てる
というところまではいっていないけれども」と、ときどき思って見て
、そのつど心に満足を覚えるのであった。
さて或る日、巳之助がランプの
見た。その柱の上の方には腕のような木が二本ついていて、その腕木
には白い瀬戸物のだるまさんのようなものがいくつかのっていた。
こんな奇妙なものを道のわきに立てて何にするのだろう、と思いながら
少し先にゆくと、また道ばたに同じような高い柱が立っていて、
それには
この奇妙な高い柱は五十
立っていた。
巳之助はついに、ひなたでうどんを
すると、うどんやは「電気とやらいうもんが今度ひけるだげな。
そいでもう、ランプはいらんようになるだげな」と答えた。
巳之助にはよくのみこめなかった。電気のことなどまるで
知らなかったからだ。ランプの代りになるものらしいのだが、
そうとすれば、電気というものはあかりにちがいあるまい。
あかりなら、家の中にともせばいいわけで、何もあんなとてつもない
柱を道のくろに何本もおっ立てることはないじゃないかと、
巳之助は思ったのである。
それから
この間立てられた道のはたの太い柱には、黒い綱のようなものが
数本わたされてあった。黒い綱は、柱の腕木にのっているだるま
さんの頭を一まきして次の柱へわたされ、そこでまただるまさん
の頭を一まきして次の柱にわたされ、こうしてどこまでもつづいていた。
注意してよく見ると、ところどころの柱から黒い綱が二本ずつ
だるまさんの頭のところで別れて、家の
のであった。
「へへえ、電気とやらいうもんはあかりがともるもんかと思ったら、
これはまるで綱じゃねえか。雀や
と巳之助が一人であざわらいながら、知合いの甘酒屋にはいって
ゆくと、いつも
ランプが、横の壁の辺に取りかたづけられて、あとにはそのランプ
をずっと小さくしたような、石油入れのついていない、変なかっこう
のランプが、
「何だやい、変なものを吊したじゃねえか。あのランプはどこか
悪くでもなったかやい」
と巳之助はきいた。すると甘酒屋が、
「ありゃ、こんどひけた電気というもんだ。火事の心配がのうて、
明かるうて、マッチはいらぬし、なかなか便利なもんだ」
と答えた。
「ヘッ、へんてこれんなものをぶらさげたもんよ。これじゃ
甘酒屋の店も何だか間がぬけてしまった。客もへるだろうよ」
甘酒屋は、相手がランプ売であることに気がついたので、
電燈の便利なことはもういわなかった。
「なア、甘酒屋のとッつあん。見なよ、あの天井のとこを。
ながねんのランプの
ランプはもうあそこにいついてしまったんだ。
今になって電気たらいう便利なもんができたからとて、
あそこからはずされて、あんな壁のすみっこにひっかけられる
のは、ランプがかわいそうよ」
こんなふうに巳之助はランプの肩をもって、電燈のよいことは
みとめなかった。
ところでまもなく晩になって、誰もマッチ一本すらなかったのに
、とつぜん甘酒屋の店が真昼のように明かるくなったので、巳之助
はびっくりした。あまり明かるいので、巳之助は思わずうしろを
ふりむいて見たほどだった。
「巳之さん、これが電気だよ」
巳之助は歯をくいしばって、ながいあいだ電燈を見つめていた。
眼のたまが痛くなったほどだった。
「巳之さん、そういっちゃ何だが、とてもランプで
できないよ。ちょっと外へくびを出して町通りを見てごらんよ」
巳之助はむっつりと入口の
どこの家どこの店にも、甘酒屋のと同じように明かるい電燈が
ともっていた。光は家の中にあまつて、道の上にまでこぼれ出ていた。
ランプを見なれていた巳之助にはまぶしすぎるほどのあかりだった。
巳之助は、くやしさに肩でいきをしながら、これも長い間ながめていた。
ランプの、てごわいかたきが出て来たわい、と思った。いぜんに
は文明開化ということをよく言っていた巳之助だったけれど、
電燈がランプよりいちだん進んだ文明開化の利器であるという
ことは分らなかった。りこうな人でも、自分が職を失うかどうか
というようなときには、物事の判断が正しくつかなくなることが
あるものだ。
その日から巳之助は、電燈が自分の村にもひかれるようになる
ことを、心ひそかにおそれていた。電燈がともるようになれば、
村人たちはみんなランプを、あの甘酒屋のしたように壁の隅に
つるすか、倉の二階にでもしまいこんでしまうだろう。
ランプ屋のしょうばいはいらなくなるだろう。
だが、ランプでさえ村へはいって来るにはかなりめんどう
だったから、電燈となっては村人たちはこわがって、なかなか
寄せつけることではあるまい、と巳之助は、一方では安心もしていた。
しかし間もなく、「こんどの村会で、村に電燈を引くかどうかを
決めるだげな」という
一撃をくらったような気がした。強敵いよいよござんなれ、
と思った。
そこで巳之助は黙ってはいられなかった。村の人々の間に、
電燈反対の意見をまくしたてた。
「電気というものは、長い線で山の奥からひっぱって来るもんだ
でのイ、その線をば夜中に
こういうばかばかしいことを巳之助は、自分の
しょうばいを守るためにいうのであった。それをいうとき
何かうしろめたい気がしたけれども。
村会がすんで、いよいよ
きまったと聞かされたときにも、巳之助は脳天に一撃をくらった
ような気がした。こうたびたび一撃をくらってはたまらない、
頭がどうかなってしまう、と思った。
その通りであった。頭がどうかなってしまった。村会のあとで
三日間、巳之助は昼間もふとんをひっかぶって寝ていた。
その間に頭の調子が狂ってしまったのだ。
巳之助は誰かを
議長の役をした区長さんを怨むことにした。そして区長さんを
怨まねばならぬわけをいろいろ考えた。へいぜいは頭のよい人
でも、しょうばいを失うかどうかというようなせとぎわでは、
正しい判断をうしなうものである。とんでもない怨みを
菜の花ばたの、あたたかい月夜であった。どこかの村で春祭の
巳之助は道を通ってゆかなかった。みぞの中を
かがめて走ったり、
他人に見られたくないとき、人はこうするものだ。
区長さんの家には長い間やっかいになっていたので、
よくその様子はわかっていた。火をつけるにいちばん都合の
よいのは
考えていた。
しずかだといって、牛は眠っているかめざめているかわかった
もんじゃない。牛は起きていても寝ていてもしずかなものだから。
もっとも牛が
さしつかえないわけだけれども。
巳之助はマッチのかわりに、マッチがまだなかったじぶん
使われていた
あたりでマッチを
ので、手にあたったのをさいわい、火打の道具を持って来たのだった。
巳之助は火打で火を切りはじめた。火花は飛んだが、ほくちがし
めっているのか、ちっとも燃えあがらないのであった。巳之助は
火打というものは、あまり便利なものではないと思った。火が出ない
くせにカチカチと大きな音ばかりして、これでは寝ている人が
眼をさましてしまうのである。
「ちえッ」と巳之助は舌打ちしていった。「マッチを持って来りゃ
よかった。こげな火打みてえな古くせえもなア、いざというとき
間にあわねえだなア」
そういってしまって巳之助は、ふと自分の言葉をききとがめた。
「古くせえもなア、いざというとき間にあわねえ、......
古くせえもなア間にあわねえ......」
ちょうど月が出て空が明かるくなるように、巳之助の頭が
この言葉をきっかけにして明かるく晴れて来た。
巳之助は、今になって、自分のまちがっていたことが
はっきりとわかった。――ランプはもはや古い道具になった
のである。電燈という新しいいっそう便利な道具の世の中に
なったのである。それだけ世の中がひらけたのである。
文明開化が進んだのである。巳之助もまた日本のお国の人間なら、
日本がこれだけ進んだことを喜んでいいはずなのだ。
古い自分のしょうばいが失われるからとて、世の中の進むのに
じゃましようとしたり、何の怨みもない人を怨んで火をつけよう
としたのは、男として何という見苦しいざまであったことか。
世の中が進んで、古いしょうばいがいらなくなれば、男らしく
、すっぱりそのしょうばいは
しょうばいにかわろうじゃないか。――
巳之助はすぐ家へとってかえした。
そしてそれからどうしたか。
寝ているおかみさんを起して、今家にあるすべてのランプに
石油をつがせた。
おかみさんは、こんな
きいたが、巳之助は自分がこれからしようとしていることを
きかせれば、おかみさんが止めるにきまっているので、
黙っていた。
ランプは大小さまざまのがみなで五十ぐらいあった。
それにみな石油をついだ。そしていつもあきないに出るときと
同じように、車にそれらのランプをつるして、外に出た。
こんどはマッチを忘れずに持って。
道が西の
春のことでいっぱいたたえた水が、月の下で銀盤のようにけぶり
光っていた。池の岸にははんの木や柳が、水の中をのぞくような
かっこうで立っていた。
巳之助は
さて巳之助はどうするというのだろう。
巳之助はランプに火をともした。一つともしては、それを池の
ふちの木の枝に吊した。小さいのも大きいのも、とりまぜて、
木にいっぱい吊した。一本の木で吊しきれないと、
そのとなりの木に吊した。こうしてとうとうみんなのランプを
三本の木に吊した。
風のない夜で、ランプは一つ一つがしずかにまじろがず、燃え、
あたりは昼のように明かるくなった。あかりをしたって寄って来た
魚が、水の中にきらりきらりとナイフのように光った。
「わしの、しょうばいのやめ方はこれだ」
と巳之助は一人でいった。しかし立去りかねて、ながいあいだ
両手を
ランプ、ランプ、なつかしいランプ。ながの年月なじんで来た
ランプ。
「わしの、しょうばいのやめ方はこれだ」
それから巳之助は池のこちら側の
向こう側の岸の上にみなともっていた。五十いくつがみなともっていた。
そして水の上にも五十いくつの、さかさまのランプがともっていた。
立ちどまって巳之助は、そこでもながく見つめていた。
ランプ、ランプ、なつかしいランプ。
やがて巳之助はかがんで、足もとから石ころを一つ拾った。
そして、いちばん大きくともっているランプに
力いっぱい投げた。パリーンと音がして、大きい火がひとつ消えた。
「お前たちの
と巳之助はいった。そしてまた一つ石ころを拾った。
二番目に大きかったランプが、パリーンと鳴って消えた。
「世の中は進んだ。電気の時世になった」
三番目のランプを割ったとき、巳之助はなぜか涙がうかんで
来て、もうランプに
こうして巳之助は今までのしょうばいをやめた。
それから町に出て、新しいしょうばいをはじめた。本屋になったのである。
*
「巳之助さんは今でもまだ本屋をしている。もっとも今じゃだいぶ
年とったので、
と東一君のおじいさんは話をむすんで、
巳之助さんというのは東一君のおじいさんのことなので、東一君は
まじまじとおじいさんの顔を見た。いつの間にか東一君はおじいさんの
まえに坐りなおして、おじいさんのひざに手をおいたりしていたのである。
「そいじゃ、残りの四十七のランプはどうした?」
と東一君はきいた。
「知らん。次の日、旅の人が見つけて持ってったかも知れない」
「そいじゃ、家にはもう一つもランプなしになっちゃった?」
「うん、ひとつもなし。この台ランプだけが残っていた」
とおじいさんは、ひるま東一君が持出したランプを見ていった。
「損しちゃったね。四十七も誰かに持ってかれちゃって」
と東一君がいった。
「うん損しちゃった。今から考えると、何もあんなことをせんでも
よかったとわしも思う。
ぐらいのランプはけっこう売れたんだからな。岩滑新田の南にある
ほかにも、ずいぶんおそくまでランプを使っていた村は、あったのさ。
しかし何しろわしもあの頃は元気がよかったんでな。
思いついたら、深くも考えず、ぱっぱっとやってしまったんだ」
「馬鹿しちゃったね」
と東一君は孫だからえんりょなしにいった。
「うん、馬鹿しちゃった。しかしね、東坊――」
とおじいさんは、きせるを
「わしのやり方は少し馬鹿だったが、わしのしょうばいのやめ方は、
自分でいうのもなんだが、なかなかりっぱだったと思うよ。
わしの言いたいのはこうさ、日本がすすんで、自分の古いしょうばい
がお役に立たなくなったら、すっぱりそいつをすてるのだ。
いつまでもきたなく古いしょうばいにかじりついていたり、
自分のしょうばいがはやっていた昔の方がよかったといったり、
世の中のすすんだことをうらんだり、そんな
決してしないということだ」
東一君は黙って、ながい間おじいさんの、小さいけれど意気の
あらわれた顔をながめていた。やがて、いった。
「おじいさんはえらかったんだねえ」
そしてなつかしむように、かたわらの古いランプを見た。